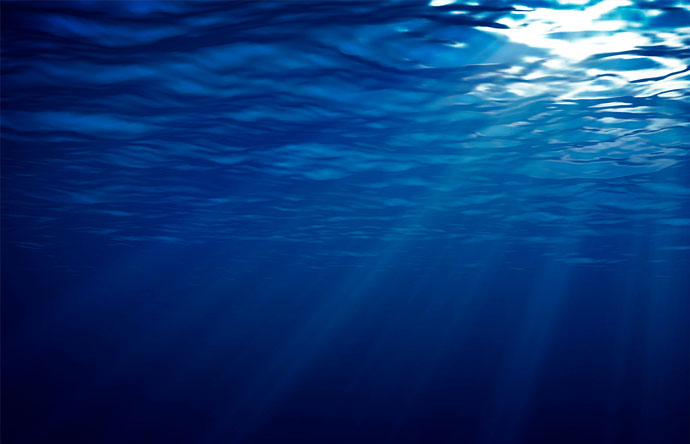これからのMODECのために
新卒で入社し勤続10年目を迎えたマネージャーが、自身の業務やMODECについて語ります。

2015年4月入社
新卒採用
東京大学大学院 工学系研究科 システム創成学専攻
技術部
プロフィール
| 2015.04 - 2019.04 | 技術部
|
|---|---|
| 2019.04 - 2020.03 | シンガポール駐在
|
| 2020.03 - 現在 | 技術部
|
| 2022.04 - 現在 | 技術部
|
| 2023.01 - 現在 | 技術部
|
| 2024.08 - 現在 | 技術部
|
私のミッション Floating Solutions for the Future
新卒採用で入社して以来、私はエンジニアとしてFPSO事業の様々なプロジェクトに参加し、操業中のFSOの補修や新規FPSOのPre Operation、アセットマネジメントなどの業務に携わってきました。ブラジル、米国等へもたびたび出張し、シンガポール駐在も経験しました。
6年目に入った2020年終盤、当時の技術部長からのアサインメントにより、MODECのR&Dに携わることになりました。Mini Projectsと呼んでいる小規模なR&Dプロジェクト群に対し予算を取り始めたものの、ほとんど進捗がない状態だったため、その進捗管理&予実管理がミッションでした。当時の私は、ベトナムのFSOのsubsea工事のプロジェクト・マネージャーとして工事完了後の仕舞い付けをしていたところで、コロナ禍で次の仕事も決まっていませんでした。今までと毛色の違う仕事でひとつのチャレンジだと思えたこと、技術部の価値向上に資するとも思えたこと、そして翌年に第一子の誕生を控えており東京勤務でできる仕事であったことなどから、二つ返事で引き受けました。
それまでのMODECのR&Dは、数は極めて少ないものの、一つ一つが大掛かりでした。それに対してMini Projectsは、小規模のプロジェクトがいくつも同時に走ります。それぞれのプロジェクトのメンバーは1人から多くても3人程度。大規模R&Dプロジェクトのように組織内にサポート人員を置く余裕はないので、それぞれのMini Projectを遂行するためのリソース確保・コンサルティング・社内業務プロセスとの整合性の担保・広報活動等、様々な面をサポートすることが、私の具体的な業務でした。
そのうち、プログラムマネージャーとして、新規R&Dの立ち上げや、リソース配分、個々のR&Dプロジェクト間の連携といったミッションも担うことになり、Low Carbon FPSO という脱炭素・低炭素技術関連の別のプログラムが立ち上がった際には、そちらのマネジメントも任されることになりました。
そして2024年8月、技術部内にR&D管理グループという新たなファンクショングループが新設されました。今後更なる業務領域の拡大・人員の増加が見込まれる技術部のR&Dプロジェクトに備え、その計画作成、進捗・予算管理を担うためのグループで、私は係留グループと兼任でファンクションマネージャーを担当することになりました。現在は、これまで行ってきたMini Projectへのサポート業務を組織に落とし込み、強化する傍ら、新規事業創出に向けた取り組みや、サステナビリティ関連の業務を技術面でサポートするといった「R&D/脱炭素」という私の主業務の周辺業務にも取り組んでいます。
2020年当初から見ると、R&D関連の取り組みに携わる仲間もずいぶん増え、Low Carbon FPSO/Mini Project に直接的・間接的に携わるメンバーは40-50名ほどになりました。予算規模としても10倍以上になり、やっと軌道に乗せられたのかな、と感じています。

新たなステージ On behalf of MODEC
今年は、R&D関連の取り組みを東京本社だけではなくMODECグループ全体で協調して進めていくべく、活動を広げています。シンガポールオフィスのtown hall meetingでは、 対面で700名、オンラインも含めると1,000名以上の従業員を前に、R&Dの取り組みや、その先のビジョンについてプレゼンを行いました。
また、経営企画部と連携し、サステナビリティ委員会のワーキンググループへの参加や、TCFD開示や顧客からの開示要請への対応、R&D関連のプレスリリース原稿や有価証券報告書のR&D関連記載のドラフト等の業務に技術面でのサポートも提供しています。
社内だけではなく、社外とのコミュニケーションに関わる機会も多くなり、業務レベルで社外の方と協業するのみならず、展示会等でMODECを代表して登壇する機会を得るなど、貴重な経験ができています。
今までは自分の仕事・プロジェクトに対してオーナーシップを持って取り組んでいましたが、全社としての経営方針策定に携わったり、会社としての対外コミュニケーションに携わったりする中で、「会社に対してのオーナーシップ」を感じるようになったのは、ここ最近での自分の中での大きな変革です。
私は好奇心旺盛なほうなので、一つの分野に縛られずにたくさんのテーマと接するにもかかわらず、それぞれについてそれなりの手触り感が得られることが今の仕事の魅力かな、と感じています。将来への種まきをする仕事なので、進捗が見えづらくもどかしいこともありますが、その種が想定していたように、もしくは別の文脈で芽生えたときには喜びもひとしおです。
一方で苦労したことは、どうしても情報や業務フローが自分に集約されてしまっていたことです。一時期は自分自身がボトルネックとなってしまう状況に陥ったこともあり、歯痒い思いをしていましたが、R&D管理グループの立ち上げにより、情報の結節点を分散させることで改善しました。しかしながら、もともと東京本社だけで始まったR&Dの取り組みを、海外支社も参画・協調して遂行する、という現在進行形の新たなチャレンジも鑑みると、R&Dに関しては現状のハブ&スポーク型の実行体制から更に進んで、将来的にはティール型の実行体制に移行したいと目論んでいます。
その第一歩として、生成AI「MODEC Sensei※」の活用によってMODECグループ全従業員間での情報の非対称性を軽減する、という取り組みをDigital & Analyticsチームと連携して進めようとしています。
※MODEC Sensei: いわゆる法人向けChat GPTにadd onでMODEC独自のモデル・機能を実装したもの。

新たな挑戦Vision, Mission, Core Values
2023年、MODECは次の中期経営計画の策定に合わせた「ビジョン、ミッション、コア・バリュー(MVV)」の改訂に動き始めました。本社のある東京と、米国・ヒューストン、シンガポール、ブラジルといった主要拠点の社員からメンバー6名を選出して検討チーム(通称「MVV6」)が編成されることになり、東京本社からは私が選出されました。
MVV6皆で東京に集まり、丸一週間を費やす集中討議を控える中、私は東京本社からの参加者として議論の舵取りを期待されていました。一週間という期限、中間・期末での報告義務だけが与えられ、議論の進め方も自由、MVV「のようなもの」(パーパス・クレド等含め)何を話すも自由、という気持ち良いまでの自由度で、全くもって議論をリードする自信はなかったのですが、議論を発散させないこと、参加者の言語レベルが均一でないこと、限られた時間で手戻り少なく進めることを念頭に、
①まずは中身でなくMVV「のようなもの」の定義について時間を割いて話すこと
②ハッカソン的に、成果物を作りながら議論を進めること
の2つの方針だけは決めて、あとは当たって砕けろ、という気持ちでした。
その上で当初の懸念としては、MODECの各拠点でビジネスモデルが異なることから必ずしも拠点間での利害が一致しないため、同じ価値観・同じビジョンを共有できるのだろうか、というものがありました。終わってみるとこの懸念は全くの杞憂で、議論を進める中で、各拠点を代弁するrepとして集まったMVV6の各人が、拠点を超えてMODECに対する思い・プライドといった職業人としての価値観の根本を驚くほど共有していることが分かったことは、大きな発見でした。
もともとエンジニアなので、日ごろからロジカルに考える・議論する、ということには慣れており、数日間に亘るワークショップも何度も経験しているのですが、このMVVワークショップは本当にタフでした。エモーショナルな思考であったり、英単語のwordingひとつひとつのニュアンスを議論したりといった普段使っていない頭をフル活用して一日中議論していると、毎日終業後には脳みそがオールアウトしていました。
何とか皆で期限内にMVV改訂案をまとめあげ、経営陣からもご賛同いただいたことで達成感もひとしおでしたが、議論を進める中でこの人は凄いな、と思ったMVV6のメンバーの一人から私の議論のファシリテーションに対して賞賛の言葉をもらったことが一番嬉しかったです。実は2020年にも前中計の前段でLong term visionをグローバルで議論するワークショップに参加させてもらっていたことがあったのですが、その時は語学力・知識・思考どの面をとってもまだまだ足りておらず、展開される議論を追うことで精いっぱい、という悔しい経験をしていました。このMVVワークショップの経験は2020年のsubsea工事のプロジェクト完工後、ダイナミックな仕事からは離れており、なかなか日々の仕事からは成長実感が得られていなかった当時の私にとって、3年間の積み上げの手ごたえを大きく感じることができる出来事でした。


全社的な課題 Hybrid Transitional Company
新卒入社なので他社を知りませんが、MODECは変わった会社だと思います。海外では名が知られているのに日本では全くの無名ですし、グループ全体では日本人がマイノリティなのに本社は日本にあります。それゆえcultureで見ても、本社だけが日本企業然として海外拠点から見ると異質に映るようなこともあります。しかしながら逆に海外拠点に共通してみられる日本企業らしい良さも多分にありますし、本社においても人数が少ないこともあって、いわゆるJTCとは異なり、担当者レベルの事象の意思決定は早いです。
10年前と比較すると、企業として次のステージへの脱皮を果たすべく奮闘中との見方もできます。グローバルで拠点や従業員もずいぶん増えましたが、グループ全体でガバナンス強化が重要視される中、それぞれの良さをどう活かしてHarmorizeしていくか。「仕事が面白い、いい仕事がしたい」というのがMODECで活き活きと仕事をしている人の共通点であり、機動的に「なんとかする」ことがMODECの強みだと考えているので、標準化・形式化という必要不可欠なプロセスの中でその良さを失いたくないと思います。

次のステージへ Attract the world
個人としての目標は、「人間力の向上」です。「人が、人と共に、人のために、何かを為す」という社会の根本が変わらない限り、人間味・人間としての魅力といったものは、このVUCAな時代においてさえ、50年後も100年後も、「いい仕事」の源泉として色褪せることはないと信じています。
世界中の多種多様な文化を持つ人々から受け入れられたい、というありたい姿を実現することは並大抵のことではないとはわかっていますが、誠実な仕事や自己の研鑽、異文化への理解等々を通じて、世界中に、私のために一肌脱いでやろうというサポーターを、そして私がその人のために助力を惜しまない、と心から思えるような繋がりを数多く作っていきたいと考えています。 そして、微力ながら自身の「いい仕事」で、直接的な関係者の枠を超えてMODECの魅力を世界に、そして日本に気付かせることに貢献できるといいなと考えています。
就活中のみなさんへ
MODEC IS FULL OF POTENTIAL
企業の寿命は30年、とよく言われます。先細ると言われる石油ガス産業に身を置くこともあり、MODECが無くなった世界を想像してみたこともあります。すると不思議とネガティブなイメージは浮かばず、MODEC OBが世界中・色々な産業でインパクトを与えている姿が想像できました。 なぜだろう、と考えたところ、きっと社員一人一人の「オーナーシップ」のなせることだろう、と納得しました。 オーナーシップを持った個人個人が、自分の可能性を、そしてMODECの可能性を”Unlock”していく、そんな仲間に是非来ていただきたいです。